ポカポカ陽気で気づいたらうたた寝…。のんびりできるときは気持ちがよいですが、忙しいときや仕事中にも眠くなってしまうのは困りもの。日中の眠気は、気候や睡眠不足だけでなく、日々の食習慣による影響もあるかもしれません。そこで今回は、中医学士で漢方薬剤師の大久保愛先生が、眠気対策となる食薬習慣と、NG習慣を教えてくれます!
毎日の食事が日中の眠気を引き起こしているかも
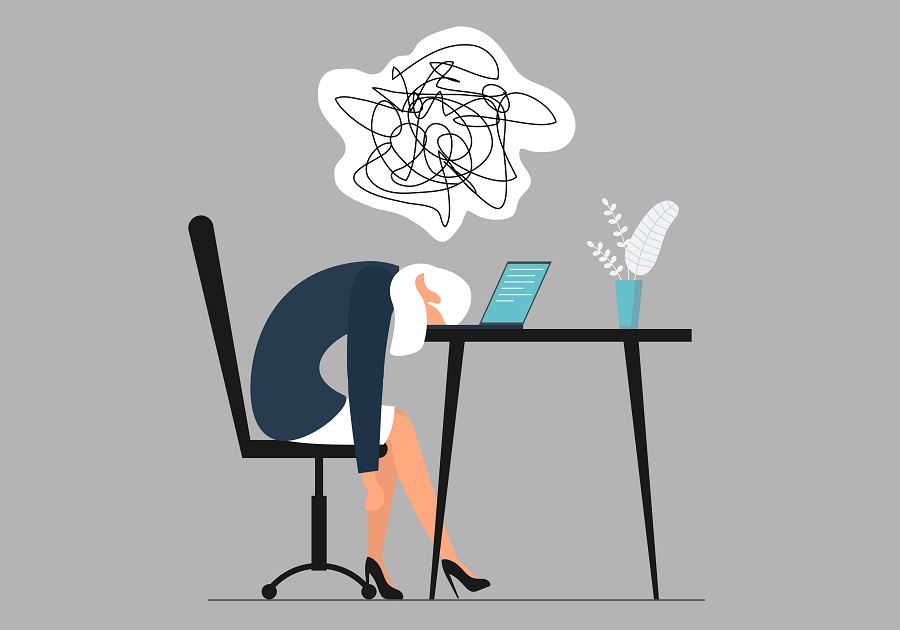
【カラダとメンタル整えます 愛先生の今週食べるとよい食材!】vol. 267
暑いなと感じる日もありますが、まだまだ穏やかな気候が続きますね。こんな気候が続くと、二度寝やうたた寝も気持ちよくなってしまいます。ただ、仕事中などやるべきことがあるときまで眠くなってしまっては問題ですよね。ポカポカ陽気の中、気持ちがよくウトウトしてしまうこともありますが、食事が原因で眠くなってしまうこともあります。仕事中や人の話を聞いているときなど、絶対に寝てはいけないときに限って眠くなってしまう人は、食事内容にも注目してみましょう。
忙しいときや、ちょっと暑いなと思う今の時期に食べたくなるものといえば、食べやすいパンであったり、喉越しの良いお蕎麦やそうめんなどの麺類ではないでしょうか。麺類の中でも、健康的でスルッと食べられるということで、お蕎麦をチョイスしている人も多いかもしれません。ですが、健康に気づかっているはずが、どうしても日中に眠くなるという人もいるのではないでしょうか。そこで、今週は日中の眠気対策となる食薬習慣を紹介していきます。
今週は、日中の眠気対策となる食薬習慣
毎日、朝は眠くてやる気が出ず、ランチが気晴らしになり元気になったと思ったら、猛烈に午後から眠くなるということはないでしょうか。そして、一日が終わる夜にかけて目が冴えていき、寝つきが悪くなるという日もあるかもしれません。そんな日がたまにはあってもよいかもしれませんが、大事な日であったり、毎日続くようであれば、今すぐなんとかしたいですよね。ただ、何から始めたらよいのかわからないということもあると思います。
このように日中眠くなり、集中力が低下している状態を、漢方医学では『血虚』、そして食後に眠くなる状態を『脾気虚』と呼んでいます。これらが起こる原因は、消化に負担がかかったり、血糖値が急上昇するような食事をとっていたり、栄養のバランスが偏っていることなどがあります。そこで、まず午後の眠気に悩んだら『脾』に負担をかけないようにランチは腹7〜8分目程度に抑えたり、消化に負担のかかるものを控えるのがよいと思います。
また、蕎麦やラーメン、うどん、丼ものなどは、糖質が多かったり、タンパク質やビタミン、ミネラルなどの摂取が不足しやすいメニューでもあるので、なるべく定食スタイルのランチを準備するのがよいでしょう。いざというときに眠い、集中力がないという人には、『脾』を強化し、『気血』を補う食薬がおすすめです。
今週食べるとよい食薬は、【大根の肉巻き 甘辛味噌仕立て】です。そして逆にNG習慣は、【お蕎麦ランチ】です。
お蕎麦は種類や食べ方によっては、体にプラスです。ですが、健康そうなお蕎麦も選び方によっては、日中の眠気にマイナスになることもあります。また、朝にパン、昼に麺類といった糖質を多くとり過ぎた食事が習慣化されている人も気をつけましょう。
食薬ごはん【大根の肉巻き 甘辛味噌仕立て】
お弁当にもおすすめな豚バラ巻です。『気血』を補い元気をつける豚肉で、『脾』に優しく胃や腸を整える大根を巻いた1品がおすすめ。ニンニクが気になる人は、なくても大丈夫です。
<材料>
豚バラ肉 150g
大根 8センチくらい(半月切り)
ニンニク 2片(スライス)
味噌・豆板醤 各小さじ1
みりん・酒 各大さじ1
<作り方>
大根をレンジで5分くらい柔らかくなるまで加熱。大根に豚肉を巻き、ニンニクと一緒に両面焼く。調味料を合わせたものを全体になじませたら完成。
NG行動【ランチのお蕎麦】
そば粉には、ポリフェノールの一種で抗酸化作用が高く、血管を丈夫にしたり、生活習慣病の予防にもなるルチンが含まれています。さらに、食物繊維、ビタミンB1、B2、ミネラルなども含まれ食薬としても優秀です。ですが、お蕎麦と一言でいっても、様々な種類があることは皆さんご存じだと思います。一般的に私たちがスーパーやランチなどで目にするお蕎麦は、小麦粉の比率が多いものが多い印象です。
実際、蕎麦には体によい働きが期待されることから健康的なイメージをもちがちですが、1食分としてざる蕎麦と定食を比べると、バランス的に糖質が多く、タンパク質や食物繊維、ビタミン、ミネラルが少なくなってしまうこともあります。眠気や集中力の低下を感じるときには、栄養バランス、血糖値、胃腸への負担なども考えて選ぶようにしてみるのもよいと思います。
いつもと比べるとなんだか眠い、集中できない、空回りしていると感じたときには、ただただ耐えるのではなく、最近の食生活はどうだったのだろうか? と一度振り返ってみてはいかがでしょうか。そのほかにも心と体を強くするレシピは、『不調がどんどん消えてゆく 食薬ごはん便利帖』(世界文化社)や新刊『だる抜け ズボラ腎活(ワニブックス)』でも紹介しています。もっと詳しく知りたい方はぜひご覧ください。
※食薬とは…
『食薬』は、『漢方×腸活×栄養学×遺伝子』という古代と近代の予防医学が融合して出来た古くて新しい理論。経験則から成り立つ漢方医学は、現代の大きく変わる環境や学術レベルの向上など現代の経験も融合し進化し続ける必要があります。
近年急成長する予防医学の分野は漢方医学と非常に親和性が高く、漢方医学の発展に大きく寄与します。漢方医学の良いところは、効果的だけどエビデンスに欠ける部分の可能性も完全否定せずに受け継がれているところです。
ですが、古代とは違い現代ではさまざまな研究が進み明らかになっていることが増えています。『点』としてわかってきていることを『線』とするのが漢方医学だと考えることができます。そうすることで、より具体的な健康管理のためのアドバイスができるようになります。とくに日々選択肢が生じる食事としてアウトプットすることに特化したのが『食薬』です。
Information
<筆者情報>
大久保 愛 先生
漢方薬剤師、国際中医師。アイカ製薬株式会社代表取締役。秋田で薬草を採りながら育ち、漢方や薬膳に興味を持つ。薬剤師になり、北京中医薬大学で漢方・薬膳・美容を学び、日本人初の国際中医美容師を取得。漢方薬局、調剤薬局、エステなどの経営を経て、未病を治す専門家として活躍。年間2000人以上の漢方相談に応えてきた実績をもとにAIを活用したオンライン漢方・食薬相談システム『クラウドサロン®』の開発運営や『食薬アドバイザー』資格養成、食薬を手軽に楽しめる「あいかこまち®」シリーズの展開などを行う。著書『心がバテない食薬習慣(ディスカヴァー・トゥエンティワン)』は発売1か月で7万部突破のベストセラーに。『心と体が強くなる!食薬ごはん(宝島社)』、『食薬事典(KADOKAWA)』、「食薬ごはん便利帖(世界文化社)」、「組み合わせ食薬(WAVE出版)」、「食薬スープ(PHP)」など著書多数。
公式LINEアカウント@aika
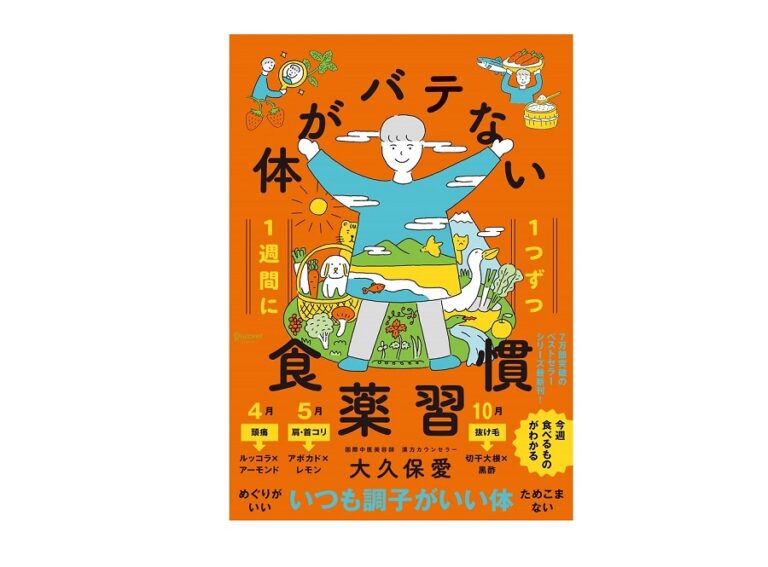
『1週間に一つずつ 心がバテない食薬習慣』(ディスカヴァー)。
『女性の「なんとなく不調」に効く食薬事典』(KADOKAWA)
体質改善したい人、PMS、更年期など女性特有の悩みを抱える人へ。漢方×栄養学×腸活を使った「食薬」を“五感”を刺激しつつ楽しく取り入れられる。自分の不調や基礎体温から自分の悩みを検索して、自分にあった今食べるべき食薬がわかる。55の不調解消メソッドを大公開。
©Azat Valeev/Adobe Stock
文・大久保愛





















































































































































