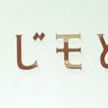小説家、エッセイスト。大学でコンピューター工学を専攻し、LG電子にソフトウェア開発者として勤務した。転職を繰り返しながらも、「毎日読み、書く人間」としてのアイデンティティーを保っている。著書に『毎日読みます』、『生まれて初めてのキックボクシング』、『このくらいの距離がちょうどいい』(いずれもエッセイ、未邦訳)。本書が初の長編小説となる。
あらすじ会社を辞めたヨンジュはソウル市内の住宅街に「ヒュナム洞書店」を立ち上げた。書店にやってくるのは、就活に失敗したバリスタのアルバイト、ミンジュン、店にコーヒー豆をおろし、夫の愚痴をこぼすジミ、人生の目標が見つからない高校生ミンチョルとその母ヒジュ、会社員の傍らブログを書き作家となったスンウ。誰もが競争社会から一歩身を引き、自分らしい生き方を模索していく。
書店の皆さんの好反応に驚き
――本屋大賞は、全国の書店員が「最も売りたい本」を投票して受賞作を選ぶ賞です。受賞を聞いてどう思いましたか?
この小説で一番心配していたのは、書店で働くみなさんがどう読んでくれるかでした。私は書店を経営したこともありませんし、アルバイトの経験もありません。書店の店長さんのエッセイなどを読んだりして書き始めたのですが、幸いにも韓国でたくさんの人に好評をいただきました。驚いたことに、日本の書店のみなさんにも同じように読んでもらえて、この賞をいただけたことでもそれが分かってうれしく思います。
受賞の知らせを聞いて、本当にすごくびっくりしました。極秘だと言われたので、今回は家族や周囲の人にも詳しい理由は伝えられずに日本へ来ることになりました。雨と聞いていたのですが天気もとても良くて、桜も咲いていて、いろんな意味でとてもうれしいです。

「2024年本屋大賞」発表会に登壇したファン・ボルムさん。「いくら努力しても人生がよくならないように思えて不安に思ったり、自分を責めたりします。そうした感情がこの小説を通して薄まってほしい。つらい世の中だからこそ、自分を応援して、他人と応援し合うような時間になればいい」とスピーチした
――主人公のヨンジュ店長は、なんだかファンさんと似ている気がします。
私に似せて書こうと思ったことは一度もないのですが、よく言われます。ヨンジュというキャラクターが好きだし、そばにいたら友だちになりたいタイプです。私が好きな接し方をしてくれて、私が求めているものを持っている人。だから「似ている」という言葉は私にとって褒め言葉です。
「休んでいいよ」物語が言ってもいい
――「ヒュナム洞」の小説は韓国で累計30万部 を突破するベストセラーとなりました。書店名には「休(ヒュ)」という字が入り、休みながら自分らしく生きていくことを書いています。その後、忙しくなったと思うのですが、休めていますか?
昨年10月にエッセイ集「単純生活者」(未邦訳)を出したのですが、そこに「『よく休んでいる』という答え」というエッセイがあります。その本のトークショーに登壇したとき、司会の方に「よく休んでいますか?」と聞かれて、「よく休んでいます」と答えたところ、「そう答える人を始めて見た」と驚かれたんです。
私も「ヒュナム洞」を書いているころは休み方がわからなくてつらかった。だからこうやって休むことの物語を書いたんです。それからは休む努力をするようになり、そのうちヒュナム洞書店と似たような生活をするようになったと思います。でも最近は休みすぎて、自分を甘やかしすぎているんじゃないかと思ったりもするんですけどね。

――休むことって実は難しいですよね。特に韓国は厳しい競争社会です。少子化が深刻な問題になっていますが、背景には過度な競争が指摘されています。
おっしゃるとおり韓国はものすごく競争が激しくて、幼いころからその環境に飛び込んでずっと走っていないといけないんです。でもそうやって走っていくと、ある瞬間で足が止まってしまう時があります。自分が止まりたくて止まったわけじゃなくても自分を責めてしまうし、追い詰めてしまう。それは自分のせいじゃなくてある種、社会の問題だし、そしてどう考えてもその時間が必要なんですよね。
休んでもいいんだと、自分を許すことが必要だと思います。それはとても大変なことです。立ち止まった時、この「ヒュナム洞」の登場人物たちのように、進む方向を点検する時間が本当は必要なのですが、点検なんてしないでまた走りたいと思ってしまう。なぜならそれしか習っていないからです。韓国は走り続けなければいけない、成功しなければならないという声が大きい社会です。だから「休んでもいいよ」と言ってくれる人が必要。そういう人がいなかったら、物語が言ってくれても良いと思います。「ヒュナム洞」の小説は、そうやって「休む時間も必要なんだ」と多くの人が考えるきっかけになったので、支持してもらえたのではと思っています。

――そんな中でファンさんはどうして休むという選択が可能だったのでしょう? かつては有名な大企業に勤めていて、韓国社会のいわゆるエリートでした。
休んでもいいという考えを持つようになったのも、両親が一度も私にプレッシャーをかけることがなかったからです。「ヒュナム洞」を書いていた時も私は無職でした。大卒で入った企業をバーンアウトで退職した後、作家になろうと7年くらいずっと何か書いていました。でもその間、家族は一度も私に「どうやって生きていくつもりなのか」とは聞かなかった。それは簡単なことではないと思います。私の姉夫婦も30歳を過ぎた私を外に連れ出し、自分の子どものように何か買ってくれたり、旅行に一緒に行ったりしてくれました。
私は30歳までは、自分みたいな娘がいれば親は楽だろうなと思っていたんです。でも、30歳で会社を辞めてからは、母に「不安じゃなかった?」と聞いたことがありますが、「あなたは大丈夫だと思っていた」ということを言ってくれました。
韓国は「成功」という道がすごく狭くて、勉強がよくできて良い大学に入り、良い会社に入ったり何かの専門家になったりしないと、失敗した人生のように言われます。その狭い道を私も突き進んできました。でも本を読んでいると、「人生の意味」といったことをたくさん探したりするじゃないですか。私は幼い頃からそういう本をたくさん読んできたからかもしれません。ここにいても意味がないのがあまりにも明白だったから、対策もせずに飛び出してしまいました。本って危ないですよね(笑)

「かもめ食堂」みたいな雰囲気を感じて
――これまでどんな本を読んできましたか?「ヒュナム洞」の小説を書く際に参考にした作品はあるでしょうか。
来年、集英社から邦訳が出る予定の『毎日読みます』というエッセイ集で、自分のことを「小説オタク」として紹介しています。小説が好きで、物語が好きで。好きな作家はたくさんいますが、今思い浮かぶのはヘルマン・ヘッセとかポール・オースターのような作家です。「毎日読みます」は読書エッセイで「本と親しくなる方法」を書いており、本をあまり読まなかった人から本好きな人に向けて50以上のエッセイを盛り込んでいます。日本の作品だと村上春樹氏や「嫌われる勇気」(岸見一郎・古賀史健、ダイヤモンド社)などがあります。
でも私は小説を書いたことがなかったので、「ヒュナム洞」は小説みたいに書きたいとは考えませんでした。「かもめ食堂」や「リトル・フォレスト」のような映画の雰囲気を出したいと考えて、それに沿って書きました。そういった雰囲気を感じ取ってもらえたらうれしいです。
――日本の読者にはどのように読まれたと思いますか? 安定した会社勤めを辞めて書店を開いた主人公ヨンジュや、受験や就職の競争社会から離脱してヒュナム洞書店に集まる人々は、韓国では「うらやましいけど、とても真似できない」。一方で日本の読者には「まわりにもそういう人はいるし、いつか自分もそうなるかも」と、より距離感が近かったのではないかという気もします。
たしかに韓国の読者からは「ファンタジーだ」と言われます。こんなことは現実にはないと。映画「かもめ食堂」も日本からフィンランドに行くという内容ですが、もう20年ほど前の作品ですし、日本にはすでにそういった文化があったのかもしれませんね。

――次の作品はどうしますか? 以前の対談では「エッセイを中心に執筆して、時々小説を書きたい」と話していました。
まだ簡単には言えませんね。私はエッセイストとして生きていくんだと思っていたんですけれど、去年の暮れから急に「物語を書きたい」と思うようになりました。「ヒュナム洞」は私が小説を書いたことがない状態で書いた作品だったのですが、その次はどう書けばよいのかというプレッシャーがあり、それをずっと引きずってきてしまいました。読者の期待に応えられるだろうかという恐怖もあります。いまは「書きたい」という欲求と、プレッシャーと恐怖が重なり合っている状態です。