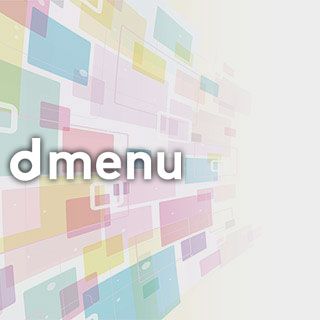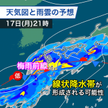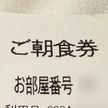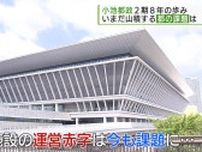現役時代に「天才」と呼ばれた元騎手の父・福永洋一が成し遂げられなかったダービー制覇を実現した福永祐一氏。20年にコントレイルで無敗のクラシック三冠を達成。23年にまさに全盛期での引退し調教師への転身を決断。自身の厩舎を開業してセカンドキャリアをスタートさせる。
(本記事は、福永祐一著『俯瞰する力 自分と向き合い進化し続けた27年間の記録』より抜粋したものです)
◆偶然がもたらしたキングヘイローとの出会い
27年間の現役生活中に行われた日本ダービーは28回。引退して改めて気づいたのは、28回中23回もその舞台に立てたという光栄な事実だった。毎年、ダービーの舞台に駒を進められるのは、選ばれし18頭と18人。そこに名を連ねることすら難しいのに、23回も依頼をもらえたこと、そしてあのダービー特有の東京競馬場の雰囲気をターフから23回も味わえたこと。それ一つを取っても、本当に幸せなジョッキー生活だったと思う。
初めて先頭でゴール板を駆け抜けたのは、19回目のダービーで、ワグネリアンに騎乗した2018年のことだった。あの勝利には“初めて味わう感情”“初めて経験した時間”、そしてそれまでのジョッキー人生における一番の喜びと感動が詰まっていた。
一番の緊張、一番の絶望、そして一番の感動──。思い起こせば、自分にいくつもの“一番”を経験させてくれた舞台、それがダービーだった。
始まりはデビュー3年目の1998年。前年9月のある日、坂口正大厩舎におじゃましていると、坂口先生のもとに一本の電話があった。その後、「(武)豊が乗れなくなったらしい」というような先生の声が聞こえてきた。そして、たまたま居合わせた自分は、先生からこう言われた。
「君、乗るか?」
そのとき、豊さんが乗れなくなった馬こそキングヘイロー。そんな偶然がすべての始まりだった。
◆ダービーまでの1週間は取材に追われる日々
10月の京都でデビューすると、新馬戦、黄菊賞、東京スポーツ杯3歳Sと3連勝。それまでにも良い馬の背中は味わっていたが、キングヘイローの背中は、それらどの馬とも違った。「やっぱり豊さんに依頼がいくような馬は違う」と思ったものだ。
その後、ラジオたんぱ杯3歳Sで2着、弥生賞3着から、クラシック第一弾である皐月賞へ。当時の自分はデビュー3年目にして、すでに上位人気馬で何度かGⅠに出走していたが、不思議なことにまったく緊張することはなかった。
それもあって、自分は緊張しないタイプの人間なのだと思っており、実際、3番人気に支持された皐月賞も平常心で挑めた。レース後に思ったのは、「これならダービーも緊張せずにいけそうだな」ということ。ダービーまでの1カ月半がどんな時間かも知らずに……。
皐月賞は、勝ったセイウンスカイから半馬身差の2着。皐月賞で1番人気3着だったスペシャルウィークを加えて、ファンやマスコミは「3強対決」だと盛り上がった。当然、自分にも取材が殺到。ほぼすべてのメディアの取材を受けていたような記憶がある。
なかでもダービーまでの1週間は、毎日のように取材に追われた。さすがにそんな経験は初めてで、取材に応えれば応えるほど“ダービー”というレースの重さがのしかかってくるようで、自分のなかでどんどんと緊張が高まっていった。うまく表現できないが、緊張が高まれば高まるほど、自分の中から“何か”が抜けていくような感覚だった。
前々日の金曜日に関西から都内へ移動し、東京競馬場まではタクシーに乗ったのだが、流れゆく外の景色を見ながらあまりにもいろいろなことを考えすぎて、逆にフワフワしていたのを覚えている。
◆レース当日に巨大なプレッシャーが襲いかかる
 レース当日は、体調が悪いわけではないのに熱っぽかった。いわゆる知恵熱というやつだと思う。とにかく朝からずっと緊張に飲まれていて、最終的にはボーッとした感じに。今思うと、緊張して固くなっているほうがまだマシだったが、そんな状態はとうに通り越し、集中力のゲージが限りなくゼロになっているような状態だった。
レース当日は、体調が悪いわけではないのに熱っぽかった。いわゆる知恵熱というやつだと思う。とにかく朝からずっと緊張に飲まれていて、最終的にはボーッとした感じに。今思うと、緊張して固くなっているほうがまだマシだったが、そんな状態はとうに通り越し、集中力のゲージが限りなくゼロになっているような状態だった。
今ならわかるが、あの状況を生んだのは、東京2400mの勝ち方を知らないという不安、ダービーに向けた心構えもよくわからないという不安など、経験のなさによる準備不足が不安を生み、それが緊張となり、最後は巨大なプレッシャーとなって襲いかかってきたのだと思う。
そうなれば、正常な判断なんてできるわけがない。返し馬では、自ら申し出てみんなとは逆の方向に行ったのだが、そこに一体どんな意図があったのか、自分でも思い出せないくらいだ。
◆我に返った4コーナー「このまま落馬してしまおうか……」
そして、いよいよゲートイン。
キングヘイローは、スペシャルウィークに次ぐ2番人気に支持されていた。1枠2番からポンとスタートを切り、皐月賞と同様、セイウンスカイがハナに行くのだろうと思いながら外を確認すると、どうやら今回は行かない様子。そして、気づいたときには自分が先頭にいた。
ウワーッと沸いているスタンド前を先頭で走りながら、まるで他人事のように「盛り上がってるなぁ」なんて思っていたのだから、完全にどうかしていた。そのまま体に力が入っていないような状態でフワーッと進んで行き、迎えた最後の4コーナー。
直線に向いたところで、後続に一気に飲み込まれた。
我に返ったのは、そのときだった。
「大変なことをしてしまった……」
直線はズルズルと下がっていきながら、「このまま帰るわけにはいかない。坂口先生に合わせる顔がない。いっそのこと落馬してしまおうか」なんて、あってはならないことを本気で考えていた。
結局、勝ったスペシャルウィークから遅れること2・6秒、14着でゴール。惨敗だった。
検量室前に引き上げていくと、そこに坂口先生の姿はなかった。その事実が何より先生の心境を物語っているように感じて、厩務員さんに「すみません……」と謝るのが精一杯。その後、何度かそのときの映像を見たが、顔面蒼白とはこういうことを言うのだと思うくらい、自分の顔は真っ白だった。
呆然自失となった自分は、マスコミの前に出ていく勇気もなく、ジョッキールームに引きこもった。すると四位さんがやってきて、「祐一、記者の人たちが待ってるから。ちゃんと喋ってこい」と優しく声をかけてくれた。
「わかりました」と答え、おぼつかない足取りで記者たちの前へ。消え入りそうな声でインタビューに答えた気がするが、何を話したのかは覚えていない。
今はもちろん、当時も、デビュー3年目の若手がダービーで2番人気の馬に乗るなんて異例中の異例だった。それでも、マスコミの取材に対し、オーナーの浅川吉男さんと坂口先生は「福永洋一が勝てなかったダービーに、息子で挑む夢があってもいいじゃないですか」と答え、その手綱を自分に託してくれた。
その思いに応えるどころか、完全に緊張に飲まれ、暴走という最悪の結果に──。
あのダービーを思い出すと、今でもいたたまれない気持ちになる。なぜなら、浅川オーナーにとって、所有馬をダービーに送り出したのはキングヘイローが最初で最後。そして坂口先生にとっても、結果的にあれが最後のダービーになってしまったのだから──。
結局、恩返しができないまま、浅川オーナーは亡くなり、坂口先生も2011年に引退。浅川オーナーの生産馬と所有馬は息子である昌彦さんが継がれたものの、今度は自分が引退してしまった。御恩を返せなかったという心の痛みは、生涯消えることはないだろう。
◆キングヘイローでの経験があったことによる進化
 キングヘイローのダービーから4年後の2002年、坂口厩舎のピースオブワールドで阪神ジュベナイルフィリーズを勝つことができた。自分にとっては初めてGⅠで1番人気に支持されたレースであり、しかも単勝オッズは1・5倍。あのときも午前中から緊張感はあったが、キングヘイローでの経験があったことで、決して緊張に飲まれてしまうことはなかった。
キングヘイローのダービーから4年後の2002年、坂口厩舎のピースオブワールドで阪神ジュベナイルフィリーズを勝つことができた。自分にとっては初めてGⅠで1番人気に支持されたレースであり、しかも単勝オッズは1・5倍。あのときも午前中から緊張感はあったが、キングヘイローでの経験があったことで、決して緊張に飲まれてしまうことはなかった。
それ以降も、パフォーマンスに影響するほどに緊張したことはなく、適度な緊張感とうまくつき合ってこられたのも、ひとえにキングヘイローでのダービーの経験があったから。
後悔の念は尽きないが、それと同時に、駆け出しの頃にいかに得がたい経験をさせてもらったか、今となってはそのありがたさが骨身に沁みる。
【福永 祐一】
父は現役時代に「天才」と呼ばれた元騎手の福永洋一。 96年にデビューし、最多勝利新人騎手賞を受賞。 2005年にシーザリオでオークスとアメリカンオークスを制覇。 11年、 全国リーディングに輝き、JRA史上初の親子での達成となった。18年、日本ダービーをワグネリアンで優勝し、父が成し遂げられなかった福永家悲願のダービー制覇を実現。20年、コントレイルで無敗のクラシック三冠を達成。23年に全盛期での引退、調教師への転身を決断。自身の厩舎を開業してセカンドキャリアをスタートさせる