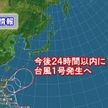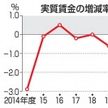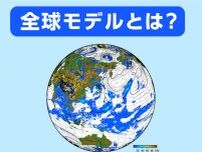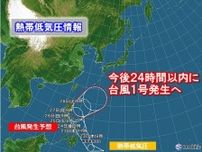お話を聞いた⼈空木春宵(うつぎ・しゅんしょう)作家
1984年静岡県生まれ。2011年、平安朝を舞台にした言語SF「繭の見る夢」で第2回創元SF短編賞の佳作に入選。21年、初の単著『感応グラン=ギニョル』を刊行し、高い評価を得た。「異形コレクション」シリーズや『夜の夢こそまこと 人間椅子小説集』などの書き下ろしアンソロジーにも短編を寄稿している。
江戸川乱歩の外連味に憧れて
――2021年刊行の第1短編集『感傷グラン=ギニョル』は、多くの幻想文学ファンに衝撃を与えました。空木さんはデビュー当初から、SFと幻想文学を融合させた独自の作風を確立していましたね。
ありがとうございます。でも本を出してみるまでは正直不安でした。SFファンからも幻想文学ファンからも、「これは違う、認められない」と言われそうな気がしていて。蓋を開けてみるとどちらも温かく迎え入れてくれて、ほっと胸をなで下ろしたという感じでした。
――デビュー作は創元SF短編賞の佳作に選ばれた「繭の見る夢」ですね。
こんなことを言うと怒られそうですが、実はそこまでSFというジャンルを意識していたわけではないんです。「繭の見る夢」は平安朝を舞台にした幻想譚で、当時そうした作品を受け入れてくれる短編の新人賞が他には見当たらなかった。創元SF短編賞は日下三蔵さん(評論家・アンソロジスト)が選考委員をされていましたし、当時東京創元社さんから刊行されていた「年刊日本SF傑作選」もかなり広義のSF作品を多数収録していたので、こういった幻想系の作品も許容してくれそうな気がしたんです。
――大学時代は国文学を専攻されていたそうですが、主にどんな分野を?
専門は『源氏物語』です。大学に入るまでは古典文学にまったく興味がなかったのですが、教養課程にて指導をしてくださった教授の人柄に惚れ込んでしまい、講義を受ける中で徐々に中古文学の面白さに目覚めました。卒論のテーマは『源氏物語』に見られる鬼と、罪の転嫁。ある意味、学生時代から興味の対象が一貫していますね(笑)。『源氏物語』は出来事や人物の心情と情景が必ずリンクしていて、たとえば登場人物の気持ちが暗くなる時は、情景も暗くなる。事件が起きる時には雨が降ってくる。そういった、いわゆる景情一致と呼ばれるような表現にも魅了されています。
――『感応グラン=ギニョル』には江戸川乱歩、谷崎潤一郎、吉屋信子など日本近代文学の影響も見え隠れしますが、読書傾向を教えていただけますか。
一番好きで影響を受けたのはやっぱり乱歩です。東京創元社から出ている『日本探偵小説全集』の存在も大きいですね。夢野久作とか久生十蘭とか、このシリーズで戦前から戦後にかけての探偵小説をまとめて読んだことは、間違いなく今の作風に繋がっていると思います。もともと母がこの手の小説が好きで、「これが面白いよ」と乱歩の『孤島の鬼』を差し出してくるような人だったことも、ある意味、恵まれていました(笑)。
――乱歩作品のどのあたりに惹かれるんでしょうか。
乱歩はあまりに巨大なので、人によって魅力に感じる部分は違うと思いますが、自分にとっては「変なことを言ってるおじさん」というイメージが一番大きいです。ミステリ作家としてすごいとか幻想作家として惹かれるとかといったこと以上に、乱歩作品に漂っている外連味、途方もなさ、大げさなところに惹かれますね。
――短編「感応グラン=ギニョル」は浅草のアングラ劇団を舞台にしていました。きらびやかな舞台芸術への関心も、乱歩と空木さんの共通点ではないでしょうか。
それは乱歩より母の影響かもしれません。母は若い頃に劇団員をやっていて、私も幼少期にエキストラとして舞台に上げられたことがあるんです。稽古の様子や裏方さんたちの仕事を眺めて、舞台はこうやって作られていくのかと子供心に感心しました。明るい表舞台とその裏側にある仕掛けへの興味は、その頃培われたものだと思います。

空木春宵さん=松嶋愛撮影
さまざまな〈呪い〉を解く物語
――今年4月には待望の第2短編集『感傷ファンタスマゴリィ』が刊行されました。表題もブックデザインも、前作を踏襲したものになっていますね。
そこは意図的に踏襲しました。テーマ的にも対になっていて、前作は〈痛みと呪い〉にまつわる短編が並んでいましたが、今回は〈呪い〉をどうやって解くかという問題に向き合った5編が収録されています。
――表題作の「感傷ファンタスマゴリィ」には、18世紀から19世紀にかけてヨーロッパで流行した、幻灯機を使って幽霊を出現させる見世物・ファンタスマゴリーが登場します。
「感応グラン=ギニョル」には浅草グラン=ギニョルという劇団が出てくるのですが、その座長が憧れているのが本場パリの残酷劇グラン=ギニョル。そしてグラン=ギニョルの流行と映画の登場によって時代遅れになったのが、光学的トリックを用いたファンタスマゴリーでした。時代的にも接点がありますし、グラン=ギニョルの次はファンタスマゴリーを題材にしようと早くから決めていました。
――「感応グラン=ギニョル」が戦前の浅草、「感傷ファンタスマゴリィ」が19世紀のパリと、ともに都市の物語でもあります。
浅草の六区とパリのパサージュ。どちらも賑やかで、でも繁栄の時代が過ぎ去った場所です。現代の我々からするとあらかじめ失われていて、かつ、当時の人たちにとっても既に古びつつあるもの。そうしたものに否応なく惹かれてしまうんです。昔は良かったというノスタルジーに陥ることを警戒しつつ、失われたものへの愛惜は描いていきたいと思います。
――主人公のノアは特殊な技術を用い、生き生きと動く幽霊を出現させます。生者にとって幽霊とは何なのかというテーマが、ノアの過去と絡み合いながら、物語後半で展開していきます。
初期プロットの立ち上げから初稿を書き上げるまでのあいだに父が他界して、死について考える機会が否応なく増えました。父は居酒屋を経営していたんですが、お通夜や告別式に来てくださった常連客の皆さんが語る生前の父の姿が、人によって大きく異なるんですよ。それは自分が知っている父の印象とも乖離があって、人それぞれの中に父が存在しているのだと気づきました。死者や幽霊をめぐる考えには、そうした思いが反映されているかと思います。

『感傷ファンタスマゴリィ』(東京創元社)
「嫌だな」ということから目を背けたくない
――2話目の「さよならも言えない」は、服装の良し悪しがスコアによって算出される時代の物語。人々は高いスコアを得るため、〈天羽槌〉という機械が生成する衣服を身にまといます。
数年前からパーソナルカラー診断や骨格診断が話題になりましたよね。自身がまとう装いを選ぶ上での指針としては役に立つものだろうと思う一方、SNS上などで「このタイプの人はこういう服装をするべき」という、他者にまでそれらを当てはめてしまう声が聞かれるようになりました。ああいう風潮にすごく違和感があって、服装くらい他人からどうこう言われることなく好きにできたらいいのにと思っていました。ファッションに限らず、昔から「何々らしく」という押しつけが大嫌いで、そういう言説には反発を覚えます。
――SF的アイデアや世界観ではなく、世の中への違和感がまずあったわけですか。
自作のほとんどはそこから出発しています。まず伝えたい感情や思いがあって、それを表現するための道具立てや物語を探っていく。基本的には自分にとって嫌なこと、違和感を覚えていることが中心になります。それを書くことで読者を啓蒙しようだとか、自作ひとつで社会を変革するだとかいう大それた考えはないのですが、これは嫌だよね、おかしいよね、と感じたことからは目を背けずにいたいと思っています。
――3話目の「4W/Working With Wounded Women」は、街の上層部に生きる人々の傷や痛みを、下層部の住人がすべて肩代わりするという物語。ある意味、究極的な格差が描かれたディストピア小説です。
これも日常感覚から生まれた作品で、体のどこかが痛かったり苦しかったりする時に、「誰かがこの苦痛を自分に押しつけているんじゃないか」と空想することがあるんです。ともすれば、対象もはっきりしない、めちゃくちゃな逆恨みなのですが(笑)。ただ、一方ではほんとうに誰かが誰かの痛みの原因となっているということも多々ありますし、それを敷衍すると、現実にある搾取の構造、たとえば、目の届かないどこか遠くで低賃金の労働者が生み出した成果物を、我々が安い値段で享受しているというような問題にも繋がってくる。それをSFとして展開させた結果、こういう物語になりました。香港を舞台のモデルにしたのも、イギリス統治下の香港という土地が正にそうした構造の縮図と思えたからです。
――以前この連載にも登場した斜線堂有紀さんの「痛妃婚姻譚」という短編が、やはり痛みを他人に移す技術を描いていました。ほぼ同時期に、よく似たアイデアの幻想小説が生まれたのは面白い現象だと思います。
完全に先を越されてしまいました。「痛妃婚姻譚」も収録されている『異形コレクション ギフト』に、自身は「死にたがりの王子と人魚姫」という短編を寄稿したのですが、実はそれと「4W/Working With Wounded Women」は元々ひとつの作品でした。「死にたがりの王子と人魚姫」で描いたのは誰も傷を負うことができない世界というものでしたが、当初はそのシステムの核を担うものを「4W/Working With Wounded Women」にも出てきた〈エコー・システム〉と設定していて、傷を負えない者と傷が送られてくる側との両面から物語を書いていたのですが、それぞれに異なるテーマを内包していると感じたのと、話が散漫になってしまったので、ふたつの作品に分けました。編集さんに「4W/Working With Wounded Women」のプロットを送った後で「痛妃婚姻譚」を読んだときには、まいったなと思いましたが(笑)ただ、他者に送られるのが痛みか、それとも、傷そのものかという点は大きく異なっているので、読み比べていただけるとより面白いかもしれません。
――4話目の「終景累ヶ辻」は、マルチバース(多元宇宙)と古典怪談が融合したユニークなSF。「累ヶ淵」「四谷怪談」「皿屋敷」などに登場する女性たちが次々に登場し、哀れにも命を落としていきます。
影響を受けたのはボルヘスの「八岐の園」という短編です。あの作品では現在が無数に分岐して存在して同時にいるのですが、反対に、過去の出来事が際限なく分岐していったらどうなるのか、という発想で怪談にアプローチしてみました。この作品の幽霊たちは、怖いというだけでなく、哀れな存在。谷中の全生庵というお寺で毎年幽霊画の展示が開かれていて、会期が来るたびに通っているのですが、幽霊画に描かれている幽霊の多くからは恨めしさ以上に寂しさや悲しみを感じさせられます。そこで、人は何も恨みのみによって幽霊になるわけではないのだろうなということも考えました。
――この「終景累ヶ辻」に顕著ですが、ルビ(振り仮名)を多用した、擬古調の文体も大きな特徴ですね。
文体については作品ごと、テーマやモチーフに沿って変えているつもりです。ただ現代風の表現よりも、「終景累ヶ辻」のような古めかしい文章の方が書いていてしっくりはきますね(笑)。ルビを多用するのは『源氏物語』の影響もあると思います。『源氏物語』は原本こそ現存しないので不明な部分も多いですが、漢字仮名交じりで書かれていたと考えられています。多くの写本を経たり、様々な全集に収められるに際して、元々はひらがなで書かれていたであろう和語に、音ではなく字義にそって後から漢字を当てたと思しき箇所があるので、すごく特殊な読みになっていることが多いんです。そうした表現の面白さ、豊かさは積極的に取り入れています。

空木春宵さん=松嶋愛撮影
10年の間に変化したエンタメの土壌
――そして最終話の「ウィッチクラフト≠マレフィキウム」は、VR空間で活動する現代の〈魔女〉を描いた作品。「さよならも言えない」と並んで、現代の社会問題がビビッドに反映されたものです。
これはもうはっきりと、性差別への怒りが執筆の原動力ですね。魔女狩りの時代、男性に従わない女性や「何をやっているのか分からない」女性は、悪しき者だとみなされ排斥された。現代はその時代からちっとも変わっていないな、とSNSを見ていて感じます。一方で20世紀後半には、フェミニズムの台頭とともに自ら魔女を名乗る女性たちが現れました。そうした主体的な動きも、現代に通じるものだと思います。
――VR空間で魔女狩りを続ける〈騎士団〉の男性を通して、性差別する側の心理にも迫っています。
人を攻撃に駆りたてるのは、おそらく正義感なのだろうなと思います。差別的な言動をくり返す人も、おそらくその人の中の正義感に突き動かされている。〈騎士団〉のメンバーにしてもそうです。逆に自分の悪性を意識している人は、あまり他者への攻撃には向かわないんじゃないでしょうか。だからこそ、自身の正しくなさを自覚することが大事なのではないかと。
――心の中に根を下ろした性差別という呪いを、私たちは解くことができるのか。物語はかすかな希望を感じさせて幕を下ろします。
『感応グラン=ギニョル』は復讐心を爆発させて、何かを崩壊させるという結末が多かったのですが、今回は呪いを解く話ですから。問題から目をそらさずに留保したまま、答えを急ぐことなく思考を続けるという結末にしなければならなかった。かと言って、答えを出すことを放棄することや、ただのきれい事になってはいけないし、そのあたりはどう表現するべきか悩みましたね。
――『感傷ファンタスマゴリィ』の発売から半月ほど経ちますが、手応えはいかがですか。
多くの方に受け入れてもらえたようで一安心しています。SNSで熱心な感想を上げてくださる方もいますし、インタビューやサイン本の依頼もいただいて、これまでの活動が実を結んできたのかなと。デビュー当時はどのジャンルの読者さんからも拒否されるのではないかという不安がありましたが、あれから10年経って、私のような作風も受け入れられる土壌が生まれつつあると感じています。それはジャンルを問わず「異形」な作品を集めてきた、「異形コレクション」の功績も大きいですよね。『感応グラン=ギニョル』を出した直後、井上雅彦先生から「異形コレクション」に誘っていただいたことは、とても励みになりました。
――今後、本格的なホラーに挑戦したいというお気持ちはありますか。
あります。私がこれまで書いてきた作品は、幻想小説的な部分はあっても、読者を怖がらせることを目的としたホラーではなかった。でもいつか脚本家の小中千昭さんが提唱されているような、ファンダメンタル(原理主義的)なホラー、恐怖のための恐怖を書いてみたいと思っています。
――それは楽しみです。では『感傷ファンタスマゴリィ』についてあらためて一言お願いします。
私は自分の同一性や連続性に揺らぎを感じていて、明日には別人になっているかもしれない、という不安感を常に抱えているんです。それは創作にも反映されていて、たとえばこの本の表題作はまさにそうした感覚を扱っています。他の収録作についても、なかなかまっすぐには前に進まない物語となっていますので、この先どこに向かうんだろうという揺らぎや不安を味わいながらページをめくっていただけたら幸いです。そういう感覚に少しでも覚えがある方なら、きっと楽しんでもらえるのではないかと思っています。